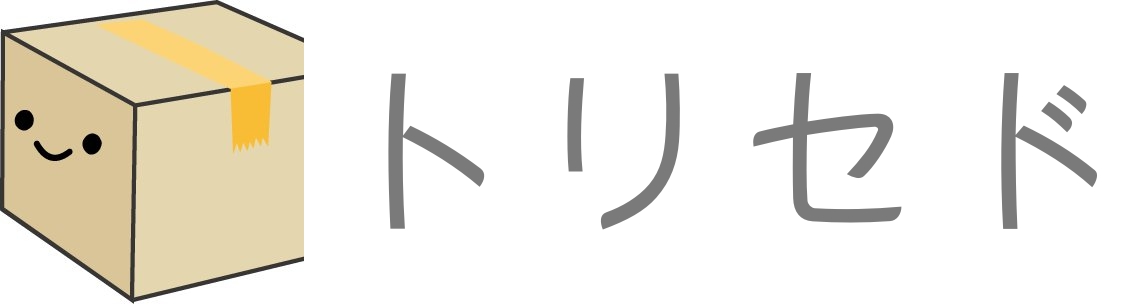使用済み切手の再利用がバレる理由と消印漏れの再使用可否

一度他の人から送られてきた切手は剥がして再利用したことが郵便局の方にバレてしまう理由と消印を押し忘れた消印がない使用済み切手はもう一度使うことができるのかについてです。
一度郵便に使用された切手は消印というスタンプ状の印が押されているので、一目で使用済切手であることがわかるようになっています。
そのため、このような消印が押されている切手を再使用することはできないようになっています。切手に押されている消印を消して再利用することは郵便法第85条に違反し、十年以下の懲役に処せられてしまうので絶対に行わないようにしてください。
切手の再利用がバレる理由
一度郵便に使った切手を再度新しい郵便物に貼り直し、再利用することは消印があるためにすぐに発覚してしまいます。消印とは、郵便局で引受された切手に押されるスタンプ状の印のことで、この消印が押されることによってその切手が使用済みであることが一目でわかるように証明されています。
そのため一度発送された切手を再利用しようとしても、使用済みの切手には消印が必ず押されるようになっているので、再利用すれば一目で発覚してしまい、郵送不可として自宅まで返送されてしまいます。
消印を消すのは犯罪
前述したように一度郵便に使用された切手は消印が押されます。また、このように切手に押されている消印を消すことは犯罪であり、万が一そのような行為をした場合は郵便法第85条に違反したことになり、十年以下の懲役に処すると定められています。過去には使用済みの切手を1枚1円以下でかき集め、それらの綺麗な部分だけ繋ぎ合わせて1枚の未使用切手に見せかけ、それを本物の未使用切手とわずかな交換手数料で交換していた銀行員が逮捕されるという事件がありました。
それ以外にも類似の事件は過去に沢山発生しており、いずれも犯罪として逮捕されています。このように切手の使用済切手の再使用や切手の偽造は立派な犯罪であり、発覚した場合は罪に問われるので絶対に行わないようにして下さい。
消印漏れの再使用可否
前述したように一度郵便で使用された切手は必ず消印が押されるようになっています。しかし、中には郵便局員のミスにより、切手に消印が押されていない状態で届く郵便物も稀にあります。このような消印漏れの切手であっても、実際には一度郵便に使用されている使用済み切手のため、通常の使用済切手同様に再使用は認められていません。
実際には消印がないため発覚することはまずありませんが、モラル上の問題として再使用は行わないようにして下さい。
また、中には肉眼では見えない透明インクで押される消印も存在しているので、そのような透明の消印が押されている可能性も考えると、消印漏れに見える切手でも再使用はおすすめできません。
消印が押されていない切手のはがし方
 |
切手はがしスポンジヘッドタイプ   |
消印が押されておらず、また一度も発送していない切手であれば、たとえ間違えて封筒などに貼ってしまった場合でも綺麗に剥がすことで再利用することが可能です。
切手を剥がす方法には冷蔵庫で冷やす方法や、ぬるま湯に浸す方法、電子レンジやドライヤーなどで温める方法など色々ありますが、一番のおすすめはコクヨから販売されている専用の切手はがしを利用する方法です。
切手はがしの使用方法は、直接切手にはがし液を塗りつけるのではなく、封筒など切手が貼り付いている梱包材の裏側から切手が貼られている場所にはがし液を塗布します。塗布してから数分ほど待つと綺麗に剥がれるようになります。
切手はがしは文房具店やホームセンターなどで売られています。
もしくは、Amazon・楽天市場・ヤフーショッピングでも購入できるので、買いに行く時間や売っているお店が近くになかった場合、メルカリに出品しているなど今後も切手を利用する機会が多い方は、ネット通販で購入するのもおすすめです。
関連:切手を間違えて貼ったときの剥がし方と交換方法
切手を間違えて貼ったときの剥がし方と交換方法

切手をハガキや封筒に間違えて貼ったときに、ドライヤーやアイロンなどの道具を使って剥がす方法と郵便局の窓口での交換方法についてです。
切手を間違えて貼り付けてしまった場合は、一番のおすすめの対処法は郵便局の窓口で5円の手数料を支払って新品に交換してもらうことですが、切手を一度剥がしてから貼り直すことも可能です。
切手の剥がし方には切手はがしを使う方法やぬるま湯に浸す方法、冷蔵庫に入れる方法、水で湿らせてから電子レンジで温める方法など、いろいろな方法があります。
普通の切手の綺麗な剥がし方
通常の裏を湿らせると糊状になるタイプの切手の剥がし方には以下のようにいろいろな方法があります。おすすめの方法は切手はがしを利用する方法ですが、一般家庭にあるものを使って、無料で剥がす方法もたくさんあります。
◼切手はがしを使う
切手を剥がす際、最もおすすめな方法はコクヨから出ている「切手はがし」という専用の剥がし液を利用して剥がす方法です。
使い方は直接切手にはがし液を付けてのではなく、封筒など切手が貼り付いている梱包材の裏側からはがし液を付けて、数分待つときれいに剥がれるようになります。
切手はがしは文房具屋やホームセンターなどに売られています。
もしくは、Amazon・楽天市場・ヤフーショッピングでも購入できるので、買いに行く時間や売っているお店が近くになかった場合、メルカリに出品しているなど今後も切手を利用する機会が多い方は、ネット通販で購入するのもおすすめです。
 |
切手はがしスポンジヘッドタイプ   |
◼ぬるま湯に浸す
切手はがしを使う方法の次におすすめな剥がし方は、ぬるま湯に切手を浸す方法です。
やり方としては、まず洗面器などに35℃程度のぬるま湯を用意します。封筒など剥がしたい切手が貼り付いている梱包材を、切手の周囲に余裕を持って切り離します。切り取った切手とその下地をぬるま湯につけて、10分ほど放置します。
ぬるま湯によって切手の糊が溶けてくると、切手が下地の紙からずれたり浮かび上がってくるので、お湯から出し、綺麗な水で切手に残った糊を洗い流します。
新聞や雑誌など挟み込んで乾かし、10分くらいしてからもう一度別の乾いた新聞などに挟んで乾かしてから完了です。
この方法は主に切手収集家がよくやる手法なため、すぐに剥がした切手を使用する場合であれば、糊を水で洗い落とした後からの乾かす工程は自然乾燥やドライヤーを使って乾かす方法でも問題ありません。
◼冷蔵庫で冷やす
上記のぬるま湯に浸す方法は切手マニアの間で昔から行われている古典的な剥がし方ですが、水に濡らすため失敗して駄目にしてしまうリスクもあります。
失敗して切手が使えなくなるのが心配な方におすすめの方法が、切手を冷蔵庫に入れて約20分ほど冷やす方法です。
原理としては冷蔵庫の中の乾燥状態によって、糊の湿度が乾燥して剥がれやすくするといったものです。また、低温によって糊の粘度も低くなるので一層剥がれやすくなる仕組みとなっています。
ただし、必ずしもすべての切手が剥がれるわけではないので、30分以上冷蔵庫に入れても上手く剥がれてこなかった場合は他の方法を試して下さい。
◼電子レンジで温める
上の冷蔵庫で冷やして乾燥させる方法とは反対に、湿らせてから熱で温めて切手をはがす方法もあります。
電子レンジで切手を剥がす方法は、まず切手を台紙ごと30秒ほど水に浸します。その後、電子レンジに入れ500Wの温度で30秒加熱します。より高いワット数であれば、加熱時間を短くして対応して下さい。
加熱後、電子レンジにから取り出すと切手が台紙から剥がれていれば完了です。
原理としては、水分で膨張しているものを急激に電子レンジで乾燥させたことによって、切手と台紙の間に隙間ができるので、簡単に剥がせるようになります。
◼アイロンで温める
上記の電子レンジの方法と似たような剥がし方で、アイロンを使った剥がし方もあります。
やり方は剥がしたい切手の上に湿らせた布を乗せ、その上からアイロンを掛けます。
電子レンジのときと同様、水分で膨張させた後で、乾燥させることによって剥がれやすくなるといった原理ですが、電子レンジでの方法よりも上手く剥がすのが難しいので、あまりおすすめできる剥がし方ではありません。
◼ドライヤーで温める
電子レンジ・アイロンと似たような方法で、ドライヤーを使って剥がす方法もあります。
切手を30秒ほど水に浸して湿らせてから、ドライヤーの熱を当てて乾かすことで剥がしていきます。ただし、温めすぎて切手を変色させないように注意してください。
◼蒸気をあてる
熱と湿気によって剥がす方法として、やかんや鍋などの蒸気によって切手をはがす方法もあります。
沸騰させたやかんや鍋の上に台紙に貼り付いた切手をあてることで、やかんなどの湯気による湿気と熱で切手を剥がれやすくします。
ただし、やけどには十分注意して行うようにして下さい。この方法で剥がす際は、台紙を小さなサイズに切り取ったときよりも封筒などに貼り付いたまま行うほうが火傷のリスクも少なく、おすすめです。
シール式切手の綺麗な剥がし方
近年よく利用されているシール式の切手についても通常の切手と同じ剥がし方で剥がします。◼切手はがし・ハガロンを使う
一番のおすすめの剥がし方は通常の切手と同様、「切手はがし」を使って剥がす方法です。
剥がし方は通常の切手のときと同様、切手の裏面から切手はがしの液を付けて数分放置してから剥がします。
また、シール式切手の場合は通常のシールと同じ性質のものなので、「3Mクリーナー30」などシールはがし専用液でも上手く剥がれます。
 |
3Mクリーナー30   |
◼ぬるま湯に浸す
シール式の切手でも、ぬるま湯に浸す方法でもきれいに剥がれます。
シール式の切手は収集家のためを考えて、糊の部分が二層構造になっています。これは普通の切手に粘着加工してあるだけなので、ぬるま湯に浸すと切手本来の糊が溶けることで、剥がれやすくなります。
きれいに剥がれた後は、通常の切手と同様に新聞紙などに挟んで水分をとってから再利用して下さい。
◼熱で温めてカッターなどで剥がす
シール式切手ならではの剥がし方として、ライターで炙ったりドライヤーを当てて熱を加えてから、切手の周囲からカッターなどの先端部で徐々に剥がすようにすると、きれいに剥がれます。
これは熱で切手のシール部分の糊が溶けて剥がれやすくなったところを、カッターなどの先端部で剥がしていくことで楽に剥がれやすくなる原理です。カッターの先端部で切手を傷つけないように注意して行って下さい。
切手を剥がさずにそのまま利用する方法
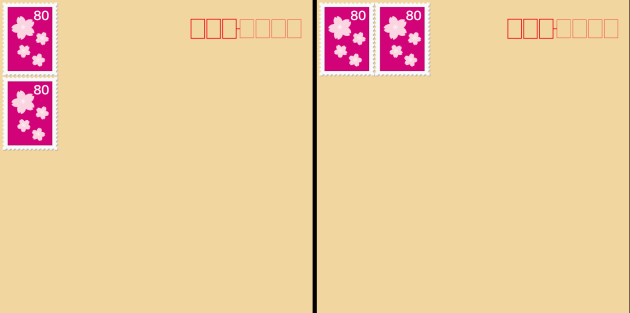
上記してきたように切手の剥がし方にはいろいろな方法がありますが、そもそも切手を剥がさずにそのまま利用するやり方もあります。
◼切り取って新しい封筒に貼り付ける
やり方としては、間違えて切手を貼ってしまった封筒を切手の周囲に沿って切り取り、それをそのまま剥がさずに新しい封筒に糊を使って貼り付けてしまうといったものです。
この方法であれば切手を剥がし損ねて駄目にしてしまうリスクもなく、安全に再利用できるので無理に剥がそうとするよりもおすすめです。
ただし、どうしても継ぎ接ぎした感じは出てしまうので大事な書類を送るような場合には行わないようにしておくと良いでしょう。
◼料金を足して速達にする
切手の料金を間違えて送料よりもオーバーして貼ってしまった場合におすすめな対処法が、無理に剥がして本来の料金分の切手を貼り直すよりも、あえて追加で切手を貼って速達や簡易書留として送ってしまうやり方です。
例えば通常の25g以下の定形郵便だと送料は84円ですが、追加で260円分を支払えば速達に、320円分を追加すれば簡易書留で送ることができます。
通常の定形郵便と比べたら送料はだいぶ高くなってしまいますが、その分速達扱いや書留扱いにして確実に届くようにできます。
間違えて切手を貼ってしまった郵便物が大事なものであれば、速達や簡易書留扱いに送ってしまえば、受取人としても決して悪い印象も受けないのでおすすめできる対処法となっています。
関連:定形郵便と定形外郵便の速達での送り方!料金・ポスト投函方法などを解説
切手の交換方法
消印が押されていない未使用の切手は、郵便局の窓口に持っていき、交換手数料を支払うことで新品の切手と交換してもらうことも可能です。交換条件としては、未使用の切手でかつ絵柄が印刷されている箇所に著しい汚れや破れ、欠けなどがない切手のみになっています。
あくまでも未使用というのは消印が押されていない状態のことを意味しているので、封筒などに貼り付けられている切手でもまだ発送していないのであれば交換対象になります。
切手の交換手数料は10円未満の1円・2円・5円切手で切手合計額の半額、10円以上の切手で1枚あたり5円となっています。
例として、2円切手・5円切手・84円切手を、それぞれ1枚ずつ交換してもらいに郵便局の窓口に持っていったとすると、合計で9円の交換手数料が発生します。
この程度の交換手数料で苦労せずに新品の切手が手に入ってしまうので、当サイトとしては無理に切手を剥がそうとするのではなく、その切手が封筒やダンボールに貼り付けられている状態で窓口に持っていき交換してもらうことをおすすめします。
関連:古い切手の有効期限・使用期限!使える切手と使えない切手を全解説
ファミリーマートでの切手の買い方と販売している切手の種類

ハガキや定形外郵便を送る際に使用する63円切手や84円切手などの切手はどこのファミリーマート(ファミマ)でも売っているのか。
ファミリーマートでの切手の買い方と販売している取り扱い切手の種類、そしてクレジットカードやTポイント等切手の支払い方法についてです。
ファミリーマートでは日本全国のほとんどすべての店舗で切手が販売されています。
そして、ファミリーマートで扱っている切手には63円切手・84円切手・94円切手など一般的によく使用されているものから、店舗によって50円切手や120円切手など一般的でないものまで、各種取り揃えています。
ファミリーマートで販売している切手の種類
| 売っている切手の種類 | |
| × 1円切手 | △ 2円切手 |
| △ 10円切手 | × 20円切手 |
| △ 50円切手 | ○ 63円切手 |
| ○ 84円切手 | ○ 94円切手 |
| △ 100円切手 | × 120円切手 |
| △ 140円切手 | × 210円切手 |
| △ 320円切手 | △ 500円切手 |
一般的にファミリーマートで扱っている切手の種類は上の表のとおりです。
○表示の切手がほとんどのファミリーマートで扱われているもの、△表示の切手がファミリーマートの店舗によって扱いがあるかどうか変わってくるもの、×表示の切手がほとんどのファミリーマートで扱われていないものとなっています。
◼84円切手はどの店舗でも売ってる
上記の表の中で最も扱われていることが多いのが84円切手となっています。
84円切手は最も頻繁に送られる定形郵便で、25g以内の郵便物を送る際に必要になります。そのため、多くの方が書類を郵送する必要になった際に最寄りのファミリーマートなどで84円切手を購入するので、多くの店舗が扱うようにしています。
その次にファミリーマートで扱われていることが多いのが63円切手と94円切手です。
63円切手は一般的な私製ハガキ(切手代わりの印刷がされていないハガキ)を送る際に必要になります。94円切手は定形郵便で50g以内の郵便物を送る際に必要になります。
書類を1枚ではなく、数枚送る場合だと基本的に25gで収まらず50g以内のサイズになってしまうので、切手も84円ではなく94円が必要になる場合が多いので、94円切手もまた需要が高くなっています。
このような理由から63円切手・84円切手・94円切手は、ほとんどどこのファミリーマートでも置かれています。
ファミリーマートの切手の料金支払い方法
| 利用できる支払い方法 | |
| ○ 現金 | ○ ファミマTカード |
| × Tポイント | × その他のクレジットカード |
| × デビットカード | × 電子マネー |
| × クオカード | × プリペイドカード |
ファミリーマートで切手の購入時に利用できる支払い方法は現金とクレジットカード機能付きのファミマTカードのみとなっています。
ローソンやセイコーマートなどでは現金のみ、セブンイレブンではnanaco、ミニストップではWAONが切手の支払い時に利用できますが、クレジットカードが利用できるのはファミリーマートだけです。
ファミリーマートで利用できるクレジットカードもファミマTカードだけではありますが、他の店では一切クレジットカードが使えない点を考えると、ここはファミリーマートの大きな強みとなっています。
また、セブンイレブンのnanacoやミニストップのWAONが切手購入時にはポイントが貯まらないのに対し、ファミマTカードでは200円につき1ポイントという、還元率0.5%でポイントが付与されます。
なお、注意点としてファミマTカードには以下の3つがあります。
1.ファミマTカード(クレジットカード)
2.ファミマTカード(Visaデビット付キャッシュカード)
3.ファミマTカード(ポイントカード)
このうち切手の購入時に利用でき、Tポイントが加算されるのは1番目のクレジットカード機能付きのファミマTカードだけですのでご注意下さい。
また、通常のTカードもまた、切手購入時に提示してもポイントは加算されませんので合わせてご注意下さい。
◼電子マネーなどでは買えない
ファミリーマートでは現金とクレジットカード機能付きファミマTカード以外の支払い方法は利用できないため、その他のクレジットカードやデビットカードでの支払いは行なえません。
切手購入時にクレジットカードを利用したい方は入会金や年会費も無料なため、ファミマTカードを作ることをおすすめします。
また、支払い時にファミマTカードが利用でき、Tポイントが加算されるとはいえ、Tポイント自体での切手購入はできませんのでご注意ください。
その他のよく利用されている支払い方法では、SuicaやPASMO、楽天Edyといったnanaco以外の各種電子マネーや、Apple Pay、楽天ペイといったスマホを用いた支払い方法もまた、切手購入時には利用できません。
なお、ファミリーマートでの切手の販売価格は、郵便局で購入した場合と同じ料金になっています。
ファミリーマートで購入したからといって郵便局で販売されている価格よりも若干料金を上乗せされていたりするようなことは絶対にありませんので、その点はご安心ください。
ファミリーマートでの切手の買い方
ファミリーマートでの切手の購入方法は、レジで店員さんに「84円切手を下さい」といったように、欲しい切手の料金を伝えるだけでOKです。もしくは374円のように単体の切手が存在しない料金の場合は、「374円分の切手を下さい」と伝えるのでもOKです。
ただし、品切れやそもそもその店舗には置いていない切手の場合もあるので、そのような場合は別の切手を組み合わせて購入するようにするか、別の店舗で購入するようにして下さい。
また、ファミリーマートには、ローソンやミニストップと違って店内に郵便ポストは設置されていません。そのため、ファミリーマートで購入した切手を貼り付けた郵便物は街中のポストに投函するか、郵便局の窓口から発送する必要があります。
参考までに、以下にファミリーマートの近くに設置されている実際の郵便ポストの集配時間を掲載します。
【東京都】ファミリーマート八王子千人町店前ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 14:30 | 14:30 | 13:10 |
| 17:30 | 17:30 |
東京都八王子市にあるファミリーマート八王子千人町店前(東京都八王子市千人町4-13-18)にあるポストの集配回数は、平日と土曜日がそれぞれ同じ時間の1日2回・日曜祝日が1日1回となっています。
【静岡県】ファミリーマート掛川柳町店前ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
静岡県掛川市にあるファミリーマート掛川柳町店前(静岡県掛川市柳町1)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日1回となっています。
【北海道】ファミリーマート苫小牧澄川町店前ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 11:15 | 11:15 | 13:40 |
| 16:15 | 16:15 |
北海道苫小牧市にあるファミリーマート苫小牧澄川町店前(北海道苫小牧市澄川町5-11-5)にあるポストの集配回数は、平日と土曜日が1日2回・日曜祝日が1日1回となっています。
関連:セブンイレブンでの切手の買い方と販売している切手の種類
セブンイレブンでの切手の買い方と販売している切手の種類

ハガキや定形外郵便を送る際に使用する63円切手や84円切手などの切手はどこのセブンイレブンでも売っているのか。
セブンイレブンでの切手の買い方と販売している取り扱い切手の種類、そしてクレジットカードや電子マネー等切手の支払い方法についてです。
セブンイレブンでは日本全国のほとんどすべての店舗で切手が販売されています。セブンイレブンで扱っている切手には63円切手・84円切手・94円切手など一般的によく使用されるものから、店舗によって20円切手や50円切手など一般的でないものまで、各種取り揃えています。
セブンイレブンで販売している切手の種類
| 売っている切手の種類 | |
| × 1円切手 | △ 2円切手 |
| △ 10円切手 | × 20円切手 |
| △ 50円切手 | ○ 63円切手 |
| ○ 84円切手 | ○ 94円切手 |
| △ 100円切手 | × 120円切手 |
| △ 140円切手 | × 210円切手 |
| △ 320円切手 | △ 500円切手 |
一般的にセブンイレブンで扱っている切手の種類は上の表のとおりです。
○表示の切手がほとんどのセブンイレブンで扱われているもの、△表示の切手がセブンイレブンの店舗によって扱いがあるかどうか変わってくるもの、×表示の切手がほとんどのセブンイレブンで扱われていないものとなっています。
◼定番は63円・84円・94円切手
上記の表の中で最も扱われていることが多いのが84円切手となっています。
84円切手は最も頻繁に送られる定形郵便で、25g以内の郵便物を送る際に必要になります。そのため、多くの方が書類を郵送する必要になった際に、最寄りのセブンイレブンなどで84円切手を購入するので、多くの店舗が扱うようにしています。
その次にセブンイレブンで扱われていることが多いのが63円切手と94円切手です。
63円切手は一般的な私製ハガキ(切手代わりの印刷がされていないハガキ)を送る際に必要になります。94円切手は定形郵便で50g以内の郵便物を送る際に必要になります。
書類を1枚ではなく、数枚送る場合だと基本的に25gで収まらず50g以内のサイズになってしまうので、切手も84円ではなく94円が必要になる場合が多く、94円切手もまた需要が高くなっています。
このような理由から63円切手・84円切手・94円切手は、ほとんどどこのセブンイレブンでも置かれています。
◼その他の切手は店舗によりけり
その他のよく置かれている切手としては100円切手などがあります。
100円切手は単体で使用されることは基本的にありませんが、他の切手と組み合わせて定形外郵便を送る際などによく使用されています。
そのため、使用頻度も高く、比較的多くの店舗が扱うようにしています。ただし、100円切手のような、63円切手・84円切手・94円切手以外の切手となると、実際に置いているかどうかについてはその店舗のオーナーの意向によって左右されてきます。
万が一、最寄りのセブンイレブンで100円切手など、上記表での△表示の切手が扱われていなかった場合は、すぐ近くの別の店舗で買い求めるようにするか郵便局の窓口で購入してください。
また高額な320円切手や500円切手になると、ほとんどのセブンイレブンで扱っていませんので、郵便局の窓口やネット通販の利用をおすすめします。
セブンイレブンの切手の料金支払い方法
| 利用できる支払い方法 | |
| ○ 現金 | ○ nanaco |
| × クレジットカード | × 電子マネー |
| × クオカード | × プリペイドカード |
セブンイレブンで切手の購入時に利用できる支払い方法は現金とnanacoのみとなっています。
ローソンやセイコーマートなどでは切手の支払いは現金のみとなっているので、セブンイレブンでnanacoを使って切手を購入できることは大きな強みとなっています。なお、ミニストップでは現金とWAONが利用できます。
注意しておきたいのは、あくまでも支払い方法としてnanacoが利用できるだけで、切手購入時にはnanacoのポイントは貯まりません。
しかし、切手購入代金分をnanacoチャージに利用できるクレジットカードなどから行うことで、間接的にそちらのクレジットカードのポイントを貯めることができます。
そのため、ローソンなどで現金で切手を購入する場合よりも、実質ポイント分お得に買うことができます。
◼クレジットカードや電子マネーでは買えない
セブンイレブンでは現金とnanaco以外の支払い方法は利用できないため、クレジットカードやデビットカードでの支払いは行なえません。日頃カード払いでセブンイレブンで買い物をしている方も、切手を買う際は現金かnanacoで支払うようにしてください。
その他のよく利用されている支払い方法では、SuicaやPASMO、楽天Edyといったnanaco以外の各種電子マネーや、Apple Pay、楽天ペイといったスマホを用いた支払い方法もまた、切手購入時には利用できませんのでご注意ください。
なお、セブンイレブンでの切手の販売価格は、郵便局で購入した場合と同じ料金になっています。
セブンイレブンで購入したからといって郵便局で販売されている価格よりも若干料金を上乗せされていたりするようなことは絶対にありませんので、その点はご安心ください。
セブンイレブンでの切手の買い方
セブンイレブンでの切手の購入方法は、レジで店員さんに「100円切手を下さい」といったように、欲しい切手の料金を伝えるだけでOKです。もしくは390円のように単体の切手が存在しない料金の場合は、「390円分の切手を下さい」と伝えるのでもOKです。
ただし、品切れやそもそもその店舗には置いていない切手の場合もあるので、そのような場合は別の切手を組み合わせて購入するようにするか、別の店舗で購入するようにして下さい。
また、セブンイレブンには、ローソンやミニストップと違って店内に郵便ポストは設置されていません。そのため、セブンイレブンで購入した切手を貼り付けた郵便物は街中のポストに投函するか、郵便局の窓口から発送する必要があります。
参考までに、以下にセブンイレブンの近くに設置されている実際の郵便ポストの集配時間を掲載します。
【東京都】セブンイレブン町田小川2丁目店前ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 13:40 | 14:05 | 12:05 |
| 16:40 | 16:55 |
東京都町田市にあるセブンイレブン町田小川2丁目店前(東京都町田市小川2-25-3)にあるポストの集配回数は、平日と土曜日が1日2回・日曜祝日が1日1回となっています。
【宮城県】セブンイレブン南方支所前店ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 15:00 | 15:00 | 09:00 |
宮城県登米市にあるセブンイレブン南方支所前店(宮城県登米市南方町新山成浦8-1)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも1日1回となっています。
【愛知県】セブン‐イレブン名古屋戸田駅前店ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
愛知県名古屋市にあるセブン‐イレブン名古屋戸田駅前店(愛知県名古屋市中川区戸田5-510)にあるポストの集配回数は、平日土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。
関連:ローソンでの切手の買い方と販売している切手の種類
ミニストップでの切手の買い方と販売している切手の種類

ハガキや定形外郵便を送る際に使用する63円切手や84円切手などの切手はどこのミニストップでも売っているのか。
ミニストップでの切手の買い方と販売している取り扱い切手の種類、そしてクレジットカードや電子マネー等切手の支払い方法についてです。
ミニストップでは日本全国のほとんどすべての店舗で切手が販売されています。ミニストップで扱っている切手には63円切手・84円切手・94円切手など一般的によく使用されるものから、店舗によって2円切手や10円切手など、各種取り揃えています。
ミニストップで販売している切手の種類
| 売っている切手の種類 | |
| × 1円切手 | △ 2円切手 |
| △ 10円切手 | × 20円切手 |
| △ 50円切手 | ○ 63円切手 |
| ○ 84円切手 | ○ 94円切手 |
| △ 100円切手 | × 120円切手 |
| △ 140円切手 | × 210円切手 |
| × 320円切手 | × 500円切手 |
一般的にミニストップで扱っている切手の種類は上の表のとおりです。
○表示の切手がほとんどのミニストップで扱われているもの、△表示の切手がミニストップの店舗によって扱いがあるかどうか変わってくるもの、×表示の切手がほとんどのミニストップで扱われていないものとなっています。
◼63円・84円・94円切手ならどこでも
上記の表の中で最も売られている確率が高いのが84円切手となっています。
84円切手は最も頻繁に送られる定形郵便で、25g以内の郵便物を送る際に必要になります。そのため、多くの方が書類を郵送する必要の際に、最寄りのミニストップなどで84円切手を購入するので、多くの店舗が扱うようにしています。
その次にミニストップで扱われていることが多いのが63円切手と94円切手です。
63円切手は一般的な私製ハガキ(切手代わりの印刷がされていないハガキ)を送る際に必要になります。また、94円切手は定形郵便で50g以内の郵便物を送る際に必要になります。
書類を1枚ではなく、数枚送る場合だと基本的に25gで収まらず50g以内のサイズになってしまうので、切手も84円ではなく94円が必要になる場合が多いので94円切手もまた需要が高くなっています。
上記の理由から63円切手と94円切手も84円切手と並んで、ほとんどどこのミニストップでも置かれています。
◼その他の品揃えは店舗ごとで異なる
その他のよく置かれている切手としては2円切手などがあります。
2円切手は当然、それ単体では郵便物を送ることはできませんが、消費税率が8%の頃に販売されていた82円切手に追加で貼ることで、84円分にしたりもできるので、使用頻度も高く、比較的多くの店舗で置いてあります。
ただし、63円切手・84円切手・94円切手以外の切手となると、実際に置いているかどうかについてはその店舗のオーナーの意向によって左右されてきます。
万が一、最寄りのミニストップで2円切手など、上記表での△表示の切手が扱われていなかった場合は、すぐ近くの別の店舗で買い求めるようにするか郵便局の窓口で購入してください。
高額な320円切手・500円切手になると、ほとんどのミニストップで扱っていませんので、郵便局の窓口やネット通販の利用をおすすめします。
ミニストップの切手の料金支払い方法
| 利用できる支払い方法 | |
| ○ 現金 | ○ WAON |
| × クレジットカード | × 電子マネー |
| × クオカード | × プリペイドカード |
ミニストップで切手の購入時に利用できる支払い方法は現金とWAONのみとなっています。
ローソンやセイコーマートなどでは切手の支払いは現金のみとなっているので、ミニストップでWAONを使って切手を購入できることは大きな強みとなっています。
注意点として、あくまでも支払い方法でWAONが利用できるだけで、切手購入時にはWAONのポイントは貯まりません。
しかし、切手購入代金分をWAONチャージに利用できるクレジットカードなどから行うことで、間接的にそちらのクレジットカードのポイントを貯めることができるので、ローソンなどで切手を購入する場合よりも、実質ポイント分お得に買うことができます。
◼クレジットカードや電子マネーでは買えない
現金とWAON以外の支払い方法は利用できないため、クレジットカードやデビットカードでの支払いは行なえません。日頃カード払いでミニストップで買い物をしている方も、切手を買う際は現金かWAONで支払うようにしてください。
その他のよく利用されている支払い方法では、SuicaやPASMO、楽天Edyといった各種電子マネーや、Apple Pay、楽天ペイといったスマホを用いた支払い方法もまた、切手購入時には利用できませんのでご注意ください。
なお、ミニストップでの切手の販売価格は、郵便局で購入した場合と同じ料金になっています。
ミニストップで購入したからといって郵便局で販売されている価格よりも若干料金を上乗せされていたりするようなことは絶対にありませんので、その点はご安心ください。
ミニストップでの切手の買い方
ミニストップでの切手の購入方法は、レジで店員さんに「94円切手を下さい」といったように、欲しい切手の料金を伝えるだけでOKです。もしくは404円のように単体の切手は存在しない料金の場合は、「404円分の切手を下さい」と伝えるのでもOKです。
ただし、品切れやそもそもその店舗には置かれていない切手の場合もあるので、そのような場合は別の切手を組み合わせて購入するようにするか、他の店舗で購入して下さい。
また、ミニストップの店内には、レジ前にコンパクトな郵便ポストが設置されています。
このポストは大きさ以外は通常の街中のポストと全く同じで日本郵便が設置しているものなので、こちらのポストにミニストップで購入した切手を貼り付けた郵便物をその場で投函して発送することができます。
ミニストップ店内ポストの集荷時間

ミニストップ店内のポストは郵便局の集配担当員がそれぞれの店舗ごとに定められている集配時間に各店を巡回して回収しています。
このポストの集配時間はそれぞれの店舗ごとによっても異なっているので、実際の集配時間はお近くのミニストップの店員さんに集配時間を確認するようにして下さい。
参考までに、以下にミニストップ店内に設置されている実際のポストの集配時間を掲載します。
【東京都】ミニストップ北区赤羽南2丁目店内ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 16:50 | 16:50 | 16:50 |
東京都北区にあるミニストップ北区赤羽南2丁目店内(東京都北区赤羽南2-9-60)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。
【神奈川県】ミニストップれこっず川崎小川町店内ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
神奈川県川崎市にあるミニストップれこっず川崎小川町店内(神奈川県川崎市川崎区小川町5-13)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。
【群馬県】ミニストップ藤岡本動堂店内ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
群馬県藤岡市にあるミニストップ藤岡本動堂店内(群馬県藤岡市本動堂833-1)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。
【京都府】ミニストップ京都東寺前店内ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 15:40 | 15:40 | 15:40 |
京都府京都市にあるミニストップ京都東寺前店内(京都府京都市南区西九条比永城町119)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。
【宮城県】ミニストップ多賀城城南店内ポスト
| 平日 | 土曜 | 休日 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
宮城県多賀城市にあるミニストップ多賀城城南店内(宮城県多賀城市城南1-11-38)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。
関連:ローソンでの切手の買い方と販売している切手の種類
スポンサードリンク